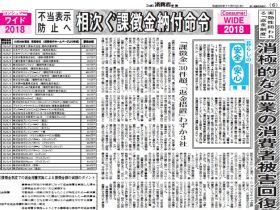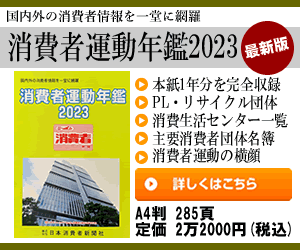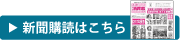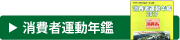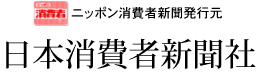カテゴリー:くらし
-

公益社団法人全国消費生活相談員協会(全相協)は、11月10日から12月2日までの土曜日と日曜日に全国3カ所で「契約トラブルなんでも110番~支払い方法についても教えてください~」という電話相談110番を開催する。
�c
-

データ偽装など反消費者的な企業不正が相次いで発覚する中、消費者庁は消費者志向経営推進へ向けた事業の一環として、11月26日、消費者志向経営優良事例を発表・表彰する。すでに外部から5人の選考委員が検討を積み重ねており、初の�c
-

公益社団法人全国有料老人ホーム協会の苦情処理委員会は10月23日から25日までの3日間、「有料老人ホームなんでも相談~有料老人ホーム110番~」を開催した。ホームなどの入居者および入居希望者から相談・苦情・意見・希望など�c
-

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)は11月3日と4日の両日、「不当請求・架空請求なんでも110番」を開催。87件の深刻相談を収集した。「これって支払わくてはいけないの?」という不�c
-
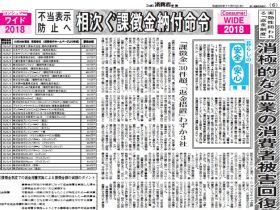
10月30日現在、不当表示に対する「課徴金納付命令」が制度導入以来、10月26日の「Life Leaf」で24社34件となった。課徴金制度は優良・有利誤認表示による不当収益を事業者から吐き出させ、違反行為の再発防止を図る�c
-

公正取引委員会事務総局中部事務所は11月21日、名古屋で毎年恒例の消費者セミナー「私たちの暮らしと公正取引委員会の関わり~安くてよい商品が買えるワケ~」を開催する。普段の買い物に深く関係している独占禁止法と景品表示法の役�c
-

主婦連合会(有田芳子会長)は11月3日、政府が来年10月に予定する消費税率アップに対し、引き上げ中止が必要との声明を発表した。「社会保障制度の改革・改善への道筋が極めて不透明な中では、いっそう消費生活への圧迫や貧困格差を�c
-

消費者庁は11月2日、株式会社「三井開発」(東京都台東区上野)に対し、特定商取引法に基づく指示処分を下した。同社は、かつて原野の土地を購入させられた消費者に「土地を買い取る」と持ちかけ、ついては「節税対策で別の土地をいっ�c
-

NIPPON 紙おむつリサイクル推進協会会長 須東亮一さん
「使用済み紙おむつ廃棄物は、ほとんどが税金による回収・焼却処理。このまま超高齢社会が到来すると処理費用増大に伴い自治体や病院、施設、そして消費者にさらに大きな�c
-

消費者庁は10月17日、平成30年度地方消費者行政の現況調査結果を発表。消費生活センターの設置数が前年比25カ所増の855か所になったことを明らかにした。また、高齢者・障害者などの消費者被害防止のための消費者安全法に基づ�c
Pickup!記事
-

コンシューマーワイド
食品ロス問題は持続可能な未来を目指す国際社会の課題になっている。SDGsは1�c
-

消費者共創と協働
夜用のショーツ型ナプキンの昼用として10月に発売した。商品名は「ズボンを脱がずに�c
-

特集
悪質商法対策プロジェクトチーム
消費者庁が立ち上げ、高市首相の国会答弁ウケ
~関�c
-

食品の流通量が増える年末に向けて、消費者庁は都道府県と連携して年末一斉取締りを実施する。年末一斉取り�c
-

冬シーズンが始まる12月に、除雪機の事故が多発しているとして、NITE(製品評価技術基盤機構)が注意�c
記事カテゴリー