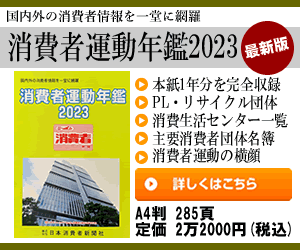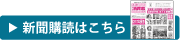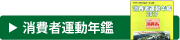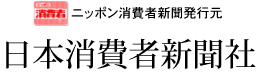高齢者の家庭内事故、転倒・転落が約半数 筋力の衰え自覚を
- 2025/10/30
- くらし
◎医療機関からの事故情報、5年で923件 国民生活センターが発生状況を分析
医療機関から寄せられる高齢者の家庭内事故のうち、約半数が「転倒」「転落」をきっかけとしたものであることが、国民生活センターの分析で明らかになった。畳や床での転倒事例も見られ、「昨日まで普通に生活できていた場所でも転倒してしまうのが高齢者の家庭内事故の特徴。筋力の低下などを自覚し、適切な対策を取ってほしい」と呼びかけている。
この分析は、参画医療機関(現在32機関)から2020年4月から今年7月末までに寄せられた65歳以上の家庭内事故923件を対象に行われた。年齢別の内訳は75歳未満が369件、75歳以上が554件と、75歳以上が多かった。
事故のきっかけは、「転倒」「転落」が全体の約半数を占めており、死亡事故も発生していた。階段や脚立で足を滑らせる、ベッドから転落する、床やレール、畳の上で転ぶなどの事故が報告されていた。例として「自宅内でスリッパが脱げ、靴下が滑って転倒。頭骨遠位端を骨折した」(70歳代・女性)、「トイレに行こうとした際に誤って階段14段を転落した」といったケースも寄せられていた。
「誤飲・誤嚥」では薬をPTPシートごと内服してしまったケースや、義歯を飲み込んでしまった事故などが報告されており、75歳未満では全体の8.9%(33件)、75歳以上では15.3%(85件)と、75歳以上の高齢者で大幅に増加していた。また、75歳以上では、認知能力の低下によるものとみられる洗剤などの誤飲・誤嚥が13件確認された。
症状別では骨折、切断、頭蓋内損傷といった重篤な事例が全体の3割を占めており、75歳以上では、菓子類や餅を詰まらせて窒息死に至るケースも見られた。
国民生活センターは2013年にも高齢者の家庭内事故に関する注意喚起を行っているが、事故の構造や発生状況は当時と大きく変わっていなかった。同センターは「高齢者の家庭内事故に対するリスクは依然として継続している」と指摘し、改めて対策を講じるよう呼びかけている。