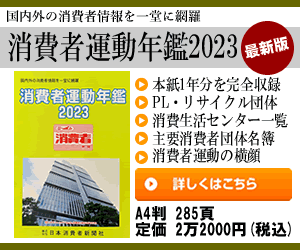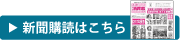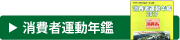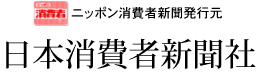見守りネットワーク連絡協議会で実践例共有、活動活性化へ交付金
- 2025/10/28
- くらし
消費者庁は10月14日、地域の高齢者・障がい者見守り活動を支援する「全国消費者見守りネットワーク連絡協議会」を会場とオンラインのハイブリット形式で開催した。消費者、福祉、障がい者、企業関係など全国から50を超える団体が参加し、情報共有や意見交換を行った。消費者庁は同協議会を全国的組織と位置付け、地域による活動をさらに活性化させる方針。地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直し、見守り活動と消費生活センターの連携強化を進めていく考えだ。
同協議会(事務局・消費者庁地方協力課)は高齢者・障がい者の消費者トラブル防止に向けた情報共有化などを目的に発足。高齢福祉や障がい者、専門職、消費生活、一般企業など各関係団体が参加し、地方自治体や関係省庁も顔をそろえる。会議は年1回を目安に開催されており、今回で21回目。新たに全国消費者協会連合会、全日本冠婚葬祭互助協会、日本証券業協会、日本郵政、全国防犯協会連合会の5団体が構成員に加わった。
当日は、構成団体の中から生命保険協会と日本介護支援専門員協会が取り組み事例を報告した。生命保険協会は、契約者宅への訪問チャネルを活かした支援活動を展開している。「生命保険は見守りネットワークに親和性のある業態。事業活動を通じて地域の課題解決に向けた取り組みを一層進めていきたい」と述べた。
一方、日本介護支援専門員協会は消費者トラブルに巻き込まれた高齢者の心理状況などについて報告した。被害に遭っても老いや認知障害を認めたくないという気持ちが働き、支援する人に対して攻撃的になる場合があるとし、「高齢者の自尊心などに配慮し、信頼関係を築いていくことから関わりを始める必要がある」と強調した。
質疑応答の時間では、各団体から「地域での活動に参加する際の窓口がわかりにくい」「活動に伴う課題の解決事例を知りたい」「耳の聞こえない消費者が電話相談をしやすい環境を整備してほしい」などさまざまな課題や要望が寄せられた。
埋もれがちな高齢者・障がい者被害を防ぐためには、啓発情報を「届ける」、活動の中で異変に「気づく」、消費生活センターに「つなぐ」という3つの機能が重要となる。消費者庁は概算要求において地方自治体向けの新たな対策を計画。「見守り活動支援員」の配置や、消費生活センターと見守りネットワークの連携強化を支援する方針だ。
消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の設置数は今年9月末現在、560自治体。総自治体数(1788)における設置割合は31%にとどまる。一方で、高齢化率は上昇し続け、2050年には37%に達する見通し。同じく、65歳以上の高齢者の約3割が認知症またはMCI(軽度認知障害)であると推計されている。
消費者庁地方協力課の赤井久宣課長は「この協議会を各地の見守りネットワークの全国的組織として位置づけ、各地の見守り活動の活性化につながるよう我々も本腰をいれて取り組んでいく」と強調。堀井奈津子消費者庁長官は「成功体験や課題の克服など地域における活動の蓄積が非常に重要であり、多くの貴重な意見をいただいた。消費者庁としても、連絡協議会を通じてさまざまな形で皆様と顔の見える関係性を築いていきたい」と協力を呼びかけた。