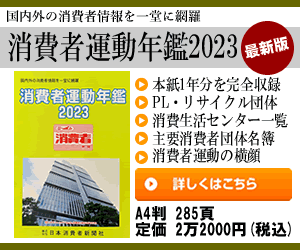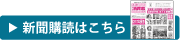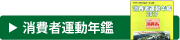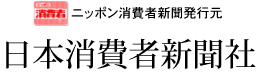日弁連がシンポジウム開催 サプリメント規制法提唱へ🔒
- 2025/3/10
- 食品
◎「リスク高く誇大広告目立つ」 被害救済制度導入も要求
死亡含む多くの腎障害の患者を発生させた「紅麹サプリメント」事故。健康被害発覚から1年。事故の全体像は依然明確ではないが、製造販売業者の小林製薬にはズサンな対応として国内外から大きな批判が出ている。事故品は機能性表示食品。国は制度の見直しに取り組み、昨年9月から届出事業者に健康被害情報の報告義務を課している。26年9月にはGMP(製造適正規範)の義務化が実施され、今年4月からは新規成分に関するデータ提出期限を販売120営業日前とすることや、提出データについても厳格な基準とされる「PRISMA(プリズマ)2020」の導入も予定。制度の指針だった「機能性表示食品の届出に関するガイドライン」は昨年8月末日に「マニュアル」へと改修、今年4月には「告示」として位置付けが強化される。「ガイドライン」から、行政関与の「告示」への転換も見直しのポイント。だがそれだけでは不十分とし日本弁護士連合会「消費者問題対策委員会」は2月14日、シンポジウムを開き、機能性表示食品を含むサプリメント形状食品には法的規制が必要性と提起した。
◎野放し状態の「サプリメント食品、早急に規制を」との意見高まる
当日のシンポジウムは、機能性表示食品制度を含む保健機能食品や、法的規制のない「いわゆる健康食品」、それらの中でもリスクが高く、問題の多いサプリメント形状食品について、法的規制の必要性を検討することが目的となった。主催は日弁連「消費者問題対策委員会」の「食品安全部会」。
講師およびパネラーには……(以下続く)
(本紙3月1日号「コンシューマーワイド」欄より一部転載)
◆この記事の続きは以下の会員制データベースサービスで購読できます
📌ジー・サーチ データベースサービス
📌日経テレコン
📌ファクティバ