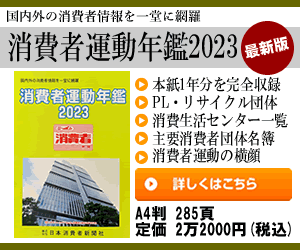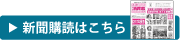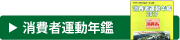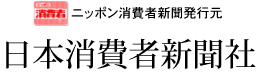国セン・山田昭典理事長 情報提供は「必要とする人に的確に」🔒
- 2025/5/16
- くらし
消費者月間特別インタビュー
◎発信チャネルをさらに多様化、SNSも駆使
消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、今年も5月の「消費者月間」を迎えた。消費者月間期間中は消費者・事業者・行政が一体となって、消費生活に関する啓発や消費者力の向上などに関連したイベントが全国で開催される。安全・安心で豊かに暮らせる社会にするためにはどうすればいいのか――。それぞれの主体が改めて考え、そして行動に移すという重要な気づきと実践の期間ともいえる。こうした消費者月間の意義を踏まえ、ニッポン消費者新聞は、消費者問題に取り組む中核的機関である国民生活センターの山田昭典理事長にインタビューを行った。山田理事長は情報を必要とする消費者に「適切・迅速に」届けるため、SNSを中心とした発信チャネルをさらに拡充させると表明。動画やアニメも駆使してアプローチ力を向上させたいと述べた。また、訪日観光客の相談対応を積極化させ、消費者庁の協力を得て大阪・関西万博での「訪日観光客消費者ホットライン」の周知に取り組んでいることも明らかにした。
◎情報発信チャネル多様化
国民生活センターの業務の重要な柱の一つが消費者への情報提供です。2022年12月に成立した「消費者契約法及び国民生活センター法の一部を改正する法律」においても、当センターの情報発信に対する期待が込められているものと認識しています。これまでやってきた情報発信を土台とし、その上にさらに積み重ねていくことが求められていると実感しています。これからも消費生活相談の場から得られた情報、商品テストなどから得られた情報を、より積極的に提示していきたいと思います。
その際に心しなければいけないことは、得られた情報をどういう人たちに届ける必要があるのか、情報を確実に届けるにはどういう手法を取ればいいのか、という視点です。確かにマスメディア向けに発表すれば情報は広く伝わることになりますが、それぞれの情報にはその情報を必要とする層が存在します。情報を必要とする消費者に適切な情報が届くよう、就任以来、きめ細やかに対応することを心がけてきました。
もはや若い世代の情報収集のルートはインターネットが中心です。しかも横長の画面であるパソコンから、縦長の画面であるスマートフォンへと移行しています。若者向けの注意喚起においては、SNSで重点的に発信し、その際は縦長の画面に収まるものとし、さらにハッシュタグを付けるなどの工夫をしています。発信チャネルの多様化にもチャレンジし、X(旧Twitter)やYouTubeに加えて……(以下続く)
(本紙「ニッポン消費者新聞」5月1日消費者月間特集号より一部転載)
◆この記事の続きは以下の会員制データベースサービスで購読できます
📌ジー・サーチ データベースサービス
📌日経テレコン
📌ファクティバ