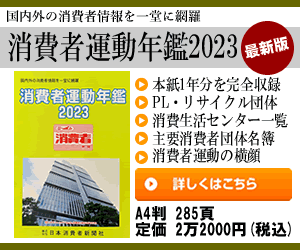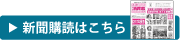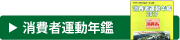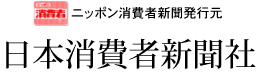93歳、栄養学者 ただの長生きではありません! 香川靖雄さん
- 2025/10/6
- くらし
ロングランシリーズ テイゲン
◎女子栄養大・香川靖雄副学長インタビュー
女子栄養大の香川靖雄副学長はことしで93歳を迎えた。現役バリバリで今も教壇に立つ。「食で健康を支える」建学の精神の体現者と言ってもいい。身をもって「健康寿命は食事から」を実践する長寿学者に食と健康について聞いた。
―自宅のある栃木県から片道2時間、電車を乗り継いで大学に通勤しているそうですね。長寿で元気の秘訣は何ですか。
厚生労働省は国民の健康の保持と増進を目的に望ましいエネルギーと栄養素の摂取量を示す食事摂取基準を定め、健康的な食事の指針となっていますが、これだけでは十分とは言えません。
わたしはこれに遺伝子栄養学、時間栄養学、精神栄養学の3つの視点を加え、実践しています。
遺伝子栄養学とは食の観点から遺伝子レベルで健康を考えることです。そこで注目すべきはビタミンの葉酸です。葉酸は遺伝子本体の核酸の合成、修復、調節に欠かせません。葉酸が欠乏すると、認知症になる確率が高まります。日本人は葉酸が欠乏する遺伝子型の人の比率が高く、少なくても1人1日400マイクログラムの摂取が求められます。
魚中心の食事を心掛けることも重要です。日本人の多くは遺伝子学的に脳や目の網膜、心臓に含まれる脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)を体内でつくれない体質で、DHAを含む魚から取る必要があります。理想的な魚の摂取量は1日100グラム。中でも脂の乗った魚がお薦めです。
―2番目に挙げた時間栄養学とは何でしょう。
朝食をきちんと取り、夜食を控える時間管理をすることです。朝食を食べないと、肥満になりやすく、朝食を取った子どもに比べて学力が落ちるデータもあります。
遺伝子の両端には「テロメア」と呼ばれる物質があります。生まれた時は1万塩基の長さがありますが、細胞分裂を繰り返すたびに短くなり、1年間に50塩基ずつ短縮されます。5000塩基になると細胞分裂が止まり、死を迎えます。やがて終わりの来る「命の砂時計」と言えるでしょう。
テロメアは適切な栄養を取り、生活習慣を改善することで短縮が鈍り、老化細胞の発達を遅らせることができます。
―3つ目の精神栄養学についてうかがいます。
歴史上の僧侶は長生きで知られています。奈良時代から明治時代にかけて日本人の平均寿命は約40歳だったのに対し、僧侶は68歳という報告があります。親鸞は迫害を受けたにもかかわらず、89歳まで生きました。当時は病院も抗生物質もなかったので僧侶らの寿命は健康寿命にほぼ等しいと思っていいでしょう。
僧侶らがなぜ長生きと言えば、節度のある食生活に加え、信仰心によって培われた「精神力」が深く関与していると考えます。105歳まで生涯現役を貫かれた聖路加国際病院名誉院長の日野原重明先生も敬虔(けいけん)なクリスチャンでした。
精神力は瞑想(めいそう)や祈祷(きとう)、ヨガ、気功でも培われます。これらが長寿につながるという考えは医学界では迷信と受け止められてきましたが、今では脳の指令に従って各組織にメッセンジャーRNA(リボ核酸)が出て、生命活動の直接エネルギーのATP(アデノシン三リン酸)合成酵素が増える研究結果も出ています。
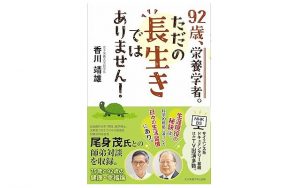 ―近著『92歳、栄養学者。ただの長生きではありません!』で紹介されている先生の日常生活は栄養バランスのある食事を規則正しく取り、適度な運動をし、気持ちを穏やかにするなど、ごく普通に過ごしているように見えます。
―近著『92歳、栄養学者。ただの長生きではありません!』で紹介されている先生の日常生活は栄養バランスのある食事を規則正しく取り、適度な運動をし、気持ちを穏やかにするなど、ごく普通に過ごしているように見えます。
学者だからと言って特別なことをしている訳ではありません。一般の人に参考にならない方法は普及しません。葉酸の摂取も魚中心の食事も無理なくできるでしょう。
―同書では「ただ長く生きるのではなく、自分の望む人生をまっとうする」と説いています。
総務省によると、2024年の65歳以上の高齢者は3625万人と過去最多で、うち90歳以上は282万人に上ります。長寿が進み、喜ばしいことですが、90歳以上の人の中で元気に働いている人はわずかで、ほとんどの人は病床に伏し、介護を受けています。
日本は少子高齢化に伴う人手不足、医療・介護費の高騰という重大な課題を抱えています。
少子化を解決するのは非常に困難。それに比べれば、お年寄りの健康寿命を延ばして社会活動できる人を増やす対策は難しくはありません。
病気や要介護のお年寄りのうち1割でも元気になってくれたら、医療や介護の世話になる人が減り、医療・介護スタッフの人手不足が軽減され、医療・介護費も抑えられます。しかも、元気になったお年寄りは医療・介護の受け手から担い手になってくれます。
本学の目指すところは食で人々の健康寿命を延ばし、自分の望む人生を長く送れるようサポートすることです。それによって国内の課題解決に貢献したいと思います。
【かがわ・やすお】1932年、東京都生まれ。東京大医学部卒、信州大医学部教授、米国コーネル大客員教授、自治医大教授、女子栄養大大学院教授を経て現職。専門は生化学・分子生物学・人体栄養学。主な著書に『生活習慣病を防ぐ』(岩波書店)『92歳、栄養学者。ただの長生きではありません!』(女子栄養大出版部)。