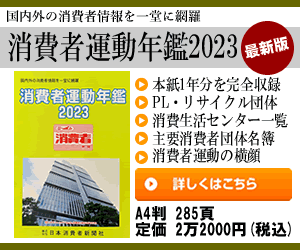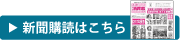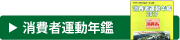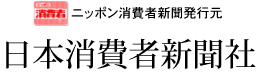健康寿命は食生活から 女子栄養大 健やか定食、葉酸活動で成果
- 2025/10/6
- 食品
コンシューマーワイド
平均寿命が「亡くなるまでの期間」を指すのに対し、健康寿命は「健康で自立して暮らせる期間」を示す。両者の差が寝たきりや認知症などで病床に伏したり、介護を受けたりする「日常生活に制限のある期間」に当たり、健康寿命を延ばし、両者の差を短くすることが社会全体の目標になっている。女子栄養大は栄養学の専門教育機関として「食により人間の健康の維持・改善を図る」ことを建学の精神に掲げ、さまざまな実践に取り組み、成果を上げている。
皿の真ん中に、ハンバーグの形をした柔らかい鶏つくね。焼き麩(ふ)とひじき、枝豆も入り、食べ応え十分だ。付け合わせの野菜が彩りを添え、主菜を引き立てる。サイの目切りのサツマイモと大豆、エリンギを和えた小鉢とご飯が付く。減塩志向でみそ汁は省かれる。
「ふわふわ!鶏つくね定食(税込み1210円)」。野菜をふんだんに使い、栄養バランスを取っている。食塩の使用量は2グラムに抑える。エネルギーも640キロカロリーと適度だ。ダイエット食品でないため、糖質は過度に低くない。
定食は「すこやかTODA定食」のラインナップの1つで9~11月、秋メニューとして埼玉県戸田市文化会館のレストラン「季の彩(ときのいろどり)」で提供される。
すこやかTODA定食は女子栄養大の学生とレストランが共同開発し、2024年にお披露目された。メニューはほかに「コク旨(うま)!酢鶏定食」「和風ロコモコ丼」「彩り野菜のドライカレー」の3種があり、季節ごとに入れ替わりでお目見えする。
レストランは健康寿命を延ばす厚生労働省の政策「健康日本21」を推進する「スマートミール(健康な食事・食環境)」制度の認証店。TODA定食もスマートミールの基準に沿う栄養価になっている。
レストランの話では、ふわふわ鶏つくね定食はデビューしたての24年9月の1カ月間で300食が出た。健康志向の女性らが注文し、「おいしくて体にも良さそう」と好評だった。
TODA定食に先だって、学生考案の「すこやかTODA弁当」も市内の飲食店で販売された。埼玉県内市町村の中で最も女性の健康寿命が短い寄居町でも同大の別の研究室の考えた「YORII KENKO弁当」が売り出されている。
すこやかTODA定食・弁当の活動を主導しているのが同大栄養学部の林芙美教授だ。
「この取り組みは行動経済学のナッジという考えの実践。ナッジとは『そっと後押しする』という意味で、強制ではなく、人々が自発的に望ましい行動を取れる環境を整えるアプローチだ。健康への意識が高い人だけでなく、『健康への関心が薄い人』も自然に健康食を取り、自然に健康になる理想に近づける目標を定めている」と話す。
その上で「栄養バランスや減塩などスマートミールの基準に合致させるばかりでなく、『ヘルシー食は見た目が物足りない』という先入観を持たれないよう、おいしそうな見栄えにすることも心掛けた」と語る。
林教授は准教授時代の23年、健康寿命を延ばす「人と地球の未来をつくる『健康な食事』実践ガイド」を研究グループのリーダーとしてまとめた。
主食、主菜、副菜別に栄養に過不足のない減塩メニューを紹介。ガイドの対象者を「自分で調理することが多い人」「買って食べる・外食が多い人」「用意されたものを食べることが多い人」とライフスタイル別に3つに分け、それぞれに合わせた献立を提案している。
健康な食事が寿命、健康寿命の延伸に効果のあることを裏付ける科学的データも明示し、説得力を高めている。
ガイドは健康の増進にとどめず、持続可能な地球と未来の構築も目指しているのが特徴だ。「人間が将来にわたって食事を取り続けられるためには、食材を安定的に生み出す環境を保つ必要がある」と食品の母体となる自然への配慮を意識している。
食品価格が高騰している中、貧富、居住地、暮らし方の違いによって入手可能な食品に差が出ないよう「誰でもどこでも適正価格で無理なく手に入れられる」環境整備を唱える。
同大の香川靖雄副学長(93)が大学キャンパスのある同県坂戸市で進める「さかど葉酸プロジェクト」も健康寿命を延ばす取り組みだ。
葉酸はビタミンの1種で脳卒中、認知症、心疾患の抑止に有効だと言われる。
プロジェクトは06年にスタートした。1人当たり1日400マイクログラムの葉酸を摂取するよう市民に呼び掛け、葉酸を多く含むホウレンソウやブロッコリーなどの緑黄色野菜、レバーを積極的に取るよう促す。
食品メーカーのハウスウェルネスフーズと共同開発した葉酸サプリ米を白米に混ぜて炊いて食べることも勧めている。市民向けの健康講座も定期的に開き、葉酸の効能と望ましい食生活を指導する。
プロジェクトを通じ、坂戸市民の健康寿命は延び、市民1人の年間医療費は34万1705円(22年度)と県内市町村の中で4番目に低くなる成果を得た。
食と健康の関係について、林教授は「健康は食だけでなく、適度な運動や禁煙、適量の飲酒、メンタルの持ちよう、生活習慣など複合的な要因が重なって左右されるが、その中でも食の占める比率は大きい」との見解を示す。
消費者に対しては「高価で特別な食材を追い求めようとすると、無理が来る。肩肘張らず(スーパーの陳列棚でよく見掛ける)あふりれた食材を買い、コンスタントに食することが長続きの秘訣(ひけつ)だ」と助言する。
最後に「最も大切なのは『食事は楽しい』ということ。栄養素を摂取することに意識が向き過ぎると、食事の楽しさがなくなる」と心構えを説く。
おいしい食事はテーブルを囲む誰とも笑顔にする。食事の魅力を堪能しながら健康づくりを進める重要性を指摘している。